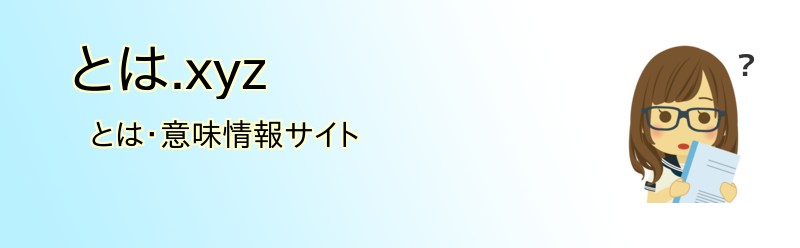
敬老の日とは?歴史・由来や祝い方を詳しく解説
毎年9月の第3月曜日は「敬老の日」です。2019年は9月16日が敬老の日ですね。
敬老の日といえば、年長の方を敬い、感謝の気持ちを伝えるための日です。みなさんも、普段お世話になっている親御さん、祖父母の方々に お祝いを贈ったり、感謝の言葉を伝えたりすると思います。しかし、その詳しい由来については意外と知らないのではないでしょうか。そこで、ここでは敬老の日に私たちがすること、各地の伝統や、喜んでもらえるプレゼントランキングを紹介していきたいと思います。
1、敬老の日とは
祝日法で「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ための日だと定められています。毎年9月の第3月曜日が敬老に日ですので、2019年でいうと9月16日です。
一般的には高齢者の方々や家族の年長の方に感謝の気持ちを伝えたり、プレゼントを贈ったりするというイメージがあると思いますが、ここではその由来や、敬老の日に私たちは誰を祝い、どのようなことをするのかを紹介していきます。
2、「敬老の日」誕生の歴史・由来
〇「としよりの日」の登場
敬老の日は、1947(昭和22)年に兵庫県のある村で「としよりの日」として生まれました。 その年の9月15日に当時の村長らが、「老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村作りをしよう」という目的で敬老会をひらき、それが「としよりの日」と呼ばれるようになりました。なぜ敬老会が9月15日だったかというと、村では1年のうちで9月中旬あたり気候がよい農閑期だったので、そのような良い時期を選んだそうです。
そして3年後の1950(昭和25)年からは、兵庫県全体に敬老会を行う風習が広がります。そしてさらに翌年には全国で行われるようになりました。
〇「老人の日」誕生
しばらくして、「としより」という表現が良くないという声が起こり、1964(昭和39)年に老人福祉法により、9月15日が「としよりの日」から「老人の日」と変わりました。
〇敬老の日 生まれる
またしばらくすると、「こどもの日や成人の日はあるのに、老人を祝う日がないのはおかしい」という意見が出ました。政府への働きかけの結果、2003(平成15)年に「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日として「敬老の日」が制定されました。
このころはまだ「敬老の日」は9月15日でした。
〇ハッピーマンデー制度の登場
2001(平成13)年、ハッピーマンデー制度により敬老の日が9月の第3月曜日へと移行します。ハッピーマンデー制度とは祝日と週休2日制をつなげ、3連休以上の期間を増やすため、国民の祝日の一部を従来の日付から特定の月曜日に移動させる制度(出典:コトバンク)です。しかしこの移行に対して反対意見も多かったため、同時に、老人福祉法の5条で、「同日(15日)から同月21日まで老人週間とする」と定められました。
このように、50年余りの時をかけて、敬老の日がうまれ、9月の第3月曜日に設定されました。
3、敬老の日に私たちがすることとは
〇感謝の気持ちを伝える
老人福祉法では老人を敬うとされていますが、普段からお世話になっている父母にも気持ちを伝えてもいいのではないでしょうか。
〇贈り物をする
敬老の日に喜ばれるプレゼント(ほしいプレゼント) 年代別 ランキング10
